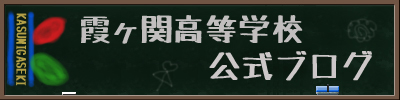[副校長] バトン
『バトン』
高校三年生にとって、夏は希望進路を実現出来るかどうかの大切な季節。本校でも就職や進学希望者が補講や面接練習に、炎暑の中を登校していた。私も面接練習を覗かせてもらった。生徒たちのどの顔にも緊張と不安が汗と共に滲み出ていた。教師生活の多くを進路指導部として送った私は面接練習の度、生徒たちに「就職でも進学でも、社会で必要とされる人となりなさい。」と話して来た。実際、自身の仕事でもそのように努めて来たと自負はしている。ところが最近、真逆の事を考えている自分がいる。「必要でない私にならねば…」と。
年齢を重ねると、手放さなければならないものや終わりにしなければならないものが多くなる。会社組織においては、定年退職というものがそれだ。私にも、そうなる年齢がすぐそこまで来ている。今まで取り組んでいたことを最後までやり遂げる事は勿論大切。自分なりにゴールまで駆け抜けたいと考えている。しかしその一方で、自分がいなくても何事もなく回る組織作りを始めることの必要性も強く感じており、その作業に着手し始めてもいる。
社会に必要とされる人になるのは、光り輝く方に歩んで行く如くワクワクする。反対に、社会に必要とされなくなるというのは言葉だけを取り上げると、なんとも寂しい響きがある。まだ生き生きと働いている者を横目に黄昏の中一人家路に向かう面持ちにも感じられる。だが、これも社会人そして働く者としての大切な役割と心得ねばならない。何故なら、社会も組織もリレーのようなものだからである。一人バトンを持って走り続けるのではなく、次の者にスムーズにバトンを渡すことまでが、チームのメンバーとして大切な役割なのだ。バトンを渡す瞬間には、次の走者が全速力で颯爽と走り去る姿を後ろから眺めたい。そこまでが社会というリレーにおける、走者としての自身の役割だと思っている。
自分としては、黄昏の中をトボトボ歩くなんてことは毛頭考えていない。家に帰ったら、あとは寝るだけなんていうのもまっぴら御免だ。バリバリ働いた日の黄昏時、アフターファイブを満喫しようと街に繰り出す心持でいたい。精一杯働いた日の仕事終わりが一番心地良いことを、経験上たっぷりと浸み込ませた身体が覚えているのだから。
次の走者が手を挙げ走り出す。必要でない私になるためのラストスパートが始まっている。
2020.9.1
霞ヶ関高等学校
副校長 伊坪 誠