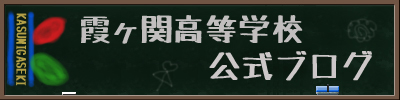[副校長] 題名「 」第七話
題名「 」第七話
誰かがいる気配がして、僕はそっと目を開けた。目の前には目力のある男性が一人、不安そうに僕をのぞき込んでいた。何歳くらいだろうか。顔には深い皺が刻まれているが、肌は艶やかで血色も良い。着ているジャケットはかなり年期の入った代物らしく、至る所に継ぎ接ぎがされている。しかし、どこもしっかりと修繕されていて、それだけでもこの男の生真面目さが感じられた。そのボロい服を絶妙に上手く着こなしている姿は、高価なブランド品を身に纏っているどの金持ち達よりも、男を気高い紳士に見せている。
「服装を着崩すことは簡単だが、着こなすことは難しい。自分を知り、社会を知り、高い知性と信念を持ち続けようとする者でないと上手な着こなしは出来ない。それは、お前のような子供でも同じ。まだ人としては未熟でも、どう生きるかを考え試行錯誤し続ける事がオシャレには大切なんだ。これは服の着こなしだけではない。生き方にも言える事なんだよ。」と僕の父親が以前話していたことを、その男をぼーっと見ながら思い出していた。
「ようやく気がついたようだね」
僕が目を開けた事に安堵したのか、男の目からは急速に不安が消えて行くのが感じ取れた。
男は傷だらけの僕を自宅に連れ帰ると、男の妻が一週間ほど介抱をしてくれた。そのお陰で元気になった僕は、10日目の午後、男と一緒に初めて外出をすることになった。日射し、空気、街路樹の葉の色、老人が出店で焼いている栗の甘く香ばしい香り、街のあちらこちらから秋の気配が感じ取れる。男にここはどこなのかを尋ねても返事は帰ってこない。しかし街の建物の様子からして、ここがヨーロッパの都市だという事は想像出来る。それもそう古い時代ではない。通りを歩く男性はスーツやジャケットを身に纏い、その人たちの多くは新聞を手にしている。
男が僕を案内してくれたのは、大きな交差点の角に建つ一軒のカフェ。学校の机を二つ横に並べた程の板で作られている看板には店の名前が鉛筆の様なもので大きく書かれていた。店の名前は「エール・ダンジュ」。「天使の翼」という意味である事を、男は僕に教えてくれた。
カフェは、活気に満ちていた。30席程だろうか。店内の席は客で埋め尽くされていた。
席では黙って新聞を読む人や本を開き何やら勉強をする人など、僕の時代のカフェとあまり違わない人の姿があった。しかしそれは入り口席のごく一部の人で、店内の客の多くは政治や経済、そして社会の諸々の話題について隣近所の人と活発に意見交換している。自分の思っていることを人に話す事を好まないとされる僕の時代の僕の国の人との大きな違いに、僕は入店すると同時に驚かされた。店内が満席なので、仕方なく僕と男は店の外に並ぶテーブル席をとることにした。5席あるテーブル席にも先客が3組いたので、あと少し遅ければ満席になっていたかもと、僕と男は顔を見合わせお互い別々の安堵のポーズをして見せて笑った。
久しぶりに笑った。小さな笑いだったが、心から笑えた。外のテーブル席に座る僕たちの肌を、爽やかな秋風がフワッと撫でて行った。それはまるで、神の祝福のようだった。
つづく
2021.9.3
霞ヶ関高等学校
副校長 伊坪 誠