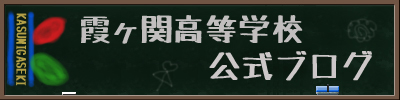[副校長] 題名「 」第八話
題名「 」第八話
男はコーヒーを二つ注文すると、街の外で倒れていた僕を見つけた時の事を詳しく話してくれた。同時に、なぜ僕が傷だらけになりながらこの街に来たのかを、出逢ってから初めて僕に訊いてきた。そして僕が何者なのかも。
僕は自分の国で開催されたコロナ禍でのオリンピックの事や、クラスでのもめ事、夢の中で見てきた様々なシーンのあらましを、男に少しばかり早口で話して聞かせた。しかし、その話を一通り終え、男の二つ目の質問に答えようとしたところで、僕は言葉が出なくなった。「僕が何者かだって? 僕は・・・僕は・・・」いくら考えてもその先が出ないのだ。日本の高校生? 夢の中での戦争中の民間人? それとも終戦末期の学生? 翼の生えた彼女を追い、走り続けるランナー? 夢の世界でも現実の社会でも、いったい僕は何者なのだろう。そもそも、高校生や日本人という肩書きを全て取り払った後に、僕には何が残っているのだろう。
今まで考えたことも無かった質問をされて、黙ったまま焦った表情の僕を男はじっと覗き込むと、大きな声で笑いだした。
数秒間の大笑いを終えると男が話し始めた。
「キミが何ものでも無いことは、初めから分かっていたよ。何者でもないから、キミはこの街に導かれて来たのだからね。」
「それはどういう意味ですか?」と僕が訪ねると、男はゆっくりとした口調で話を続けた。
「この街は、何者かになりたい何者でも無い人が集まる街なんだよ。先程、この店の中の様子を見ただろう? みんな学んだり、学んだことをベースにして活発に議論を重ねている様子を。人は誰かと意見を交わすことで何者かになれるんだ。それは職業での何者という意味もあれば、人としての何者という意味もあるんだ。ちょうど君たちの世界にはコミュニケーションという便利な言葉があるよね?」
「はい、コミュニケーションをとることは大切だと言われていますし、コミュニケーション力のある人は「コミ力のある人」と言われて、クラスでも人気者になっています。」
僕は、クラスでコミ力の高いと評されているAの事を頭に描いて話していた。Aとは僕の前に仁王立ちになった、あのグループのリーダーだ。
「人間は生まれて来たときは皆同じ。眠いだのお腹が減っただのの欲求は皆持っていて、それを親にぐずったり泣いたりして伝達するだろう? でもそれを『コミュニケーション力がある』とは言わない。ただ自分の感情を相手に伝達するだけがコミュニケーション力ならば、人間よりも動物の方が『コミュニケーション力が高い』という事になってしまうからね。」
僕は自宅で飼っている猫のミーの事を思い出した。確かにミーは、すり寄ったり泣いたりの身振りや音声で、いつも感情をストレートに表現している。
「我々人間界でいうコミュニケーション力とは、身振りや音声で欲求や情報を伝達することだけではないのだ。もちろん人間だって身振りや態度で思いを相手に伝える事はあるし必要だ。しかし、人間のコミュニケーションで忘れてならないのは、自分が思ったことや感じたことを言葉や文字、つまり「言語」にして相手にしっかりと伝える事なんだよ。それは反対に相手から受け取ることもある。そうやって他者と言語を交換しながら、お互いを分かり合うこと。それをキミの世界では、「意志の疎通」とか「心を通わす」という言葉で表現しているのではないかい?」
心を通わすという言葉では、僕の彼女の事が真っ先に浮かんだ。僕と彼女は、本当に心を通わせ合えていたのだろうか?
「では、人間がコミュニケーション力を高めるために必要な事は何だか分かるかね?」
男が不意に質問してきたので、僕は一瞬びっくりした。
「思ったり、感じたりすることかなぁ」
男の言葉をしっかりと聞いていたからこそ出た、男の言葉を利用しただけのとっさの言葉だった。それでも男は僕の答えに満足したように話を続けた。
「そうだね、先ず大切なことは様々なことについて思ったり感じたりすること。そして次に大切なのが、自分の言葉で相手に分かりやすいように伝えること。そして最後に相手の言葉を理解すること。この三つが揃うことが大切なんだ。」
「思うこと、伝えること、理解すること」
僕は男の言葉を聞き漏らすまいと、心の中で復唱した。
「しかし残念なことに、この三つの力は直ぐに身につくというものではない。長い時間をかけて身につけるしかないのだよ。」
「その長い時間の間、何をすれば良いのですか?」
僕は男の話にのめり込んで行くのを、はっきりと自覚した。
その時の僕の気持ちは、翼の生えた僕の彼女を追いかけ走っていたときの気持ちと、どこか重なって感じた。
2021.9.4
霞ヶ関高等学校
副校長 伊坪 誠