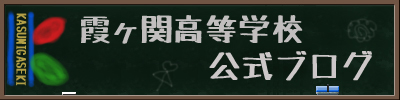[副校長] 題名「 」第五話
題名「 」第五話
鉄塔の街に近づくにつれ、沿道には村が増えてきた。それにともない僕が走るのを不思議そうに眺める見物人もどんどん増えてきた。立ち止まり僕を凝視する人もいれば、チラッとこちらに視線を向けただけで何事も無かったようにいつもの生活に戻る人。僕を見る方法は人それぞれだが、僕に向けられた見物人の大方の視線は、傷だらけになりながら走る僕に理解や好意を示すもので無いことは容易に分かった。中には走る僕に指を差しながら大声で笑い出す者や、罵声を浴びせる者もいた。彼らの中には誰一人、僕が傷だらけになりながらも走っている理由を訊ねる者はいない。僕のやっている行為が、自分たちとは違うというだけで冷ややかな視線を浴びせている者ばかりだ。
長時間走り続けてきた僕の息は、かなり荒い。それでも僕は僕が走っている理由を彼ら見物人達に理解してもらおうと、出来るだけ大きな声を絞り出し話し始めた。しかし、いくら説明しても上手く説明出来ない。上手く説明出来ないのだから、聞く方も理解など出来る筈がない。なんせ僕が説明しようとしている事は、目に見えない現実離れしている話なのだから。彼ら見物人に今見えているものは、傷だらけになり、あちらこちらから血を流し夢中で走る僕の姿だけ。彼らの関心事は目に見えている現実だけで、目に見えない理想や志などはどうでも良いのかも知れない。
僕は人に思いを伝える事の難しさを思い知らされた。同時に、もし僕が見物人側にいたとしたら、はたして僕の話に耳を傾けるだろうかとも考えてみた。話す側とそれを聞く側の在り方、それが上手く機能したときでないと、物事は良い方向には進まない。ならば、どうやったら、上手く機能させる事が出来るのだろう。「誰か教えて欲しい!」。そう思いながらも今の僕には、ありったけの大きな声で話し続けるしか術はなかった。
走りながらの大きな声での説明と激しい疲労。いつしか僕の意識は遠のいて行き、砂利道にドッと倒れた。倒れて意識がなくなって行く僕に視線を送る者は、誰も居なかった。
村は、なにごとも無かった様に、いつもの静けさに戻っていった。
つづく
2021.8.26
霞ヶ関高等学校
副校長 伊坪 誠