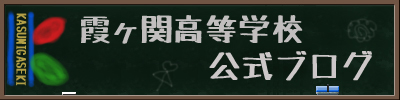[副校長] 題名「 」第四話
題名「 」第四話
翼を広げて空を舞う僕の彼女を追って、僕はオリンピック競技場を飛び出した。競技場から続く真っ直ぐな大通りを走ると、街を埋め尽くす多くの人々が僕を応援してくれた。手を高らかに挙げ声援を送る人、たなびく小旗、ひときわ大きな旗を振る大男。僕は走りながら大観衆に応援される心地良さを、生まれて初めて味わった。自分のやっている事に強く明確な意味も信念も有るわけで無いのに大声援は僕を英雄にする。少なくても僕自身の中では、僕は完全無欠な超人にでもなったかのような満足感を感じていた。街を抜けると大観衆は突然いなくなった。それでも僕は、幾つものヒマワリ畑と麦畑が続いているなだらかな丘を一人走り続けた。僕の走る姿を、麦の穂やヒマワリの花たちは黙って見ている。先程の大歓声を味わった僕は心細くなってきた。誰にも応援されないし誰も見ていないのならば、走るのを止めてしまおうかとも考えた。気持ちが沈んできている事も、はっきりと分かる。そんな僕の前を、翼の生えた僕の彼女は相変わらずゆっくりと、大きな白い翼を羽ばたかせながら南東の方角に向かって飛んで行く。その後を僕はひたすらに追いかけている。そうやって何時間も何日も走り続けて行くうちに、彼女を追いかける事が僕の走り続けている理由であり、彼女に翼が生えて飛んでいる理由を知ることが僕の走り続ける信念であると思えてきた。
昼夜走り続けている僕は、畑の中の砂利道に何度も足を滑らして転倒した。転倒する度に脚や腕は方々が切れて出血した。僕の身体からあふれ出す血は、洞窟で瀕死の状態になっていたときの血の量に匹敵する。しかし何故だろう、血が噴き出している自身の身体を見ても、洞窟の時のような恐ろしさも無念さも湧いてこなかった。流す血は同じでも、人は状況によって違う思いになる。僕は何度転倒しても、転倒した回数と同じ回だけ起き上がり走り続けて行った。転んでも起き上がる自分に、僕は少しだけ大人になったのだと確信した。
幾つ目かの朝、鉄塔のそびえる街が遠くに見えてきたところで、僕の前をひらひらと飛んでいた彼女を見失ってしまった。
それでも僕は、鉄塔の街に真っ直ぐに続いて行く畑の中の砂利道を走り続けた。
つづく
2021.8.25
霞ヶ関高等学校
副校長 伊坪 誠