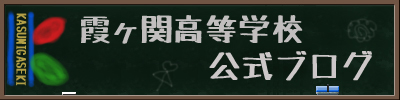[副校長] 題名「 」第三話
題名「 」第三話
次の場面は太平洋戦争末期の日本、旧制中学校の校庭。夏なのだろうか、まだ一日が始まったばかりというのに、日差しが身体を容赦なく痛めつけている。僕は同級生と前後左右定規で測ったのではと思うほど綺麗な等間隔を空け整列している。よく見ると僕らが立っているのは将棋台の上だった。僕らの前には陸軍将校らしき人が校長先生、教頭先生を従えて一段高い朝礼台の上、普段は校長先生がお話になる位置に立っている。朝礼台の前には何故だかテレビかパソコンまたはスマホのような画面が置いてあり、朝礼台の周りに立つ人と僕ら生徒との間がそれで仕切られている。壇上の将校が突然甲高い大声で生徒達に訓辞を述べ始めた。なんでも戦況もいよいよ厳しくなる中、我が国は本土決戦も視野に入れた総力戦をするそうだ。そのために、来春に中学を卒業する僕ら最上級生は進学よりも軍隊に入隊せよ。入隊しない者達も国のために軍需工場で働きたまえ。また、いざというときには武器を手に取り、敵兵と差し違える覚悟でいて欲しい。今なによりも大切なことは、この戦争に必ず勝利することで有り、そのためにも国民は我慢し犠牲を払えとのことだ。
人の命の大切さや、自分の人生は自分で描きましょうなどと校長先生が生徒達に向かって普段お話になっている朝礼台。今日、朝礼台の上から聞こえてくる話は、全く逆の話ではないか。国の都合で物事の価値や善悪の基準がコロコロと変わってしまう世の中。僕ら若者を自分たちの都合の良い様に動かそうとする国家。そもそも何よりも大切だと朝礼台の上から将校が力説していた「戦い」って、誰が何のために始めたのかも僕たちは知らない。
将校の話を聞けば聞くほど納得がいかなくなり、今すぐにでも質問したいという気持ちが湧いてきた僕は、将校の話が終わるやいなや思わず手をあげてしまった。将校は少し驚いたようであったが、直ぐに冷静さを繕った顔と声で「そこの君、何か質問かね?」と、僕に尋ねた。つかさず僕は、僕の中にある思いと疑問を将校に向けてみた。
将校の顔はみるみると赤くなり眼光鋭く僕を睨みつけた。その形相を横から見ていた教頭先生は、校庭一番左端の前から3列目にいた僕のもとに慌てて駆け寄り、僕をそこから退場させようと力一杯に僕の手を掴んだ。質問の答えを聞くまではこの場を動くまいと僕は抵抗したが、旧制中学生の僕の力では、体格の良い大人の教頭先生の力には為す術もない。あっと言う間に整列し立っていた場所から、はじき飛ばされてしまった。
そのやりとりが行われている最中、周囲の者達は誰1人微動だにしなかった。それもそのはず、つい今しがたまで同級生だと思っていた彼らは、皆将棋の駒に変わっていた。その駒には黒い墨で「歩」と筆書きされている。どの駒も小さくて薄っペらく、薄汚れていた。
校庭の端での僕と教頭先生とのやりとりがまだ続いているのに、将校は朝礼台の上からひときわ甲高い声で「今の質問についての答えを知るためには、この炎天下の校庭に直立不動のまま立ち続け20年間分の勉強を血と汗を流しながらする必要がある。それでも良いから答えを聞きたいという者は、この中にいるか?」
将校は努めて怖い表情を作りながら、薄汚れた将棋の駒達を見回した。思惑どおり駒達が無言なのを確認した将校は続けざまにこう述べた。「学ぶことが嫌いな諸君達に説明しても分からないであろう。よって、答えは割愛する。ただしこれだけは教えよう。今この国で行われている戦いは、君たちを元気にするための戦いなのだ。君たちの為を思い続けている戦いに、疑問を抱くなど100年早い! 文句が有るのなら、1000年勉強してから言いたまえ!」
将校が話し終えると校庭に立つ300枚程の駒達は一斉に振動を始め、カタカタと鳴りだした。その光景を列外から眺める事になった僕は、あることに気がついた。カタカタと音を立てている駒の中には、途中少しだけ動きを止めて考える様な仕草をする駒が有ることを。更にはカタカタという音の中にもそれぞれ特徴が有ることを。しかしそれらは目をこらし、耳を澄ませなければ気づくことの無いほど小さな違いであり、校庭や駒達を一つの塊としか見ていない将校には、同じ動きと同じ音を鳴らしている小さく薄汚れた駒にしか見えないようだ。将校は至って満足げに、片手をあげながら朝礼台から降りていった。
教頭先生に腕を腕をつかまれたまま、僕は体育館に連れて行かれた。教頭先生は体育館の扉を開けると同時に、僕を力任せに中に放り込んだ。体育館の中では、オリンピックの開会式の真っ最中。気づけば僕は、開会式の様子を壇上から右手を高らかに挙げながら見下ろしているこの国の指導者らしき人の横に立っていた。その指導者らしき男は、僕に向かってこう言った。「身振り手振りを取り入れながら派手に演説すれば、演説に内容など無くても国民を熱狂させる事が出来る。何故だか分かるかね?」。
いきなりの質問に僕が黙っていると、その男は僕が質問に答えられなかったのがとても嬉しかったらしく、満面の笑みでこう言った。「国民が馬鹿だからだよ。」「国民は馬鹿な方が、政治はし易いのだ。」「馬鹿な国民には、理論立てた説明も、根拠に基づいた政策実施も必要ない。大切なものは国民を酔わせることなんだ。それが証拠に、この開会式やオリンピックを見たまえ。私が考案した開会式での派手な演出に国民は酔いしれ、オリンピックの成功はこの国の永遠の繁栄を国民に予感させる効果を発揮している。だから私は、1936年のこの国にオリンピックを誘致したのだよ。」そう言いながら笑う男の顔には、見覚えがあった。しかし誰に似ていたのか、僕には最後まで思い出せなかった。
開会式では、真っ白な鳩が数百羽、真っ黒な体育館の天井に向け放たれた。黒い空に向かい羽ばたき舞う白い鳩。その無数の鳩の中に、翼をつけた僕の彼女を見つけた。彼女を見つけた僕は、これが夢の中の事だと気がついた。なのに、その光景を眺めている夢の中の僕は、ただただ幸せな気分になった。「馬鹿でも幸せかも」。勉強があまり好きでは無い僕の心の中に、そんな感情が湧き始めていた。
つづく
2021.8.12
霞ヶ関高等学校
副校長 伊坪 誠