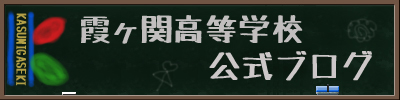[副校長」 題名「 」第二話
題名「 」第二話
夢の中で僕は幾つもの時代と場所を駆け抜けた。最初は太平洋戦争中の南の島。眠る前に鳴り響いていた雷鳴とトタンを激しく叩く豪雨の音は、敵戦艦からの艦砲射撃と、動くもの全てを標的にして撃ちまくっている戦闘機からの機銃掃射の音に変わっていた。僕がいるのは暗くジメジメとした洞窟の中、いつもと同じ体勢で横になっているのだが、何故か身体を動かすことが出来ない。僕は辛うじて動かすことが出来る首と目を使って自分の身体を見て驚いた。体中に巻かれた包帯代わりのボロ布と、そこからしたたり落ちる原油の様に粘り気を持つ黒い血。包帯が足りなかったのだろうか、湿った熱気に露わになっている傷口には無数のウジ虫が食らいついている。どうやら僕は瀕死の重傷の様だ。僕は兵隊なのか? いや民間人のようだ。なぜなら隣には泥だらけになった僕の彼女と両親が腰を下ろし泣きながら僕を見ているから。意識がはっきりすると同時に、身体中を激痛が走る。呼吸も苦しい。いくら息を吸おうとしても満足行く酸素量を確保出来いない事は、自分自身ではっきりと認識できる。
僕はうめく以外に言葉は出せない状況の様だが、傍らにいる僕の彼女と両親の会話は、はっきりと聞くことが出来た。
「もう俺たちでは、これ以上施しようがない。どの方面の医療施設も重傷者で満杯、せめて衛生兵や従軍看護師に少しの時間だけでも診てもらいたいのだが、この程度の症状の者は容体に変化が無い限りは自宅療養せよとのことらしい。」父親の沈んだ低い声が聞こえる。
「自宅療養ったて、私たちは専門家で無いのだし、必要な医療器具も薬も無いじゃない。容体が急変し慌てて保健所や救急に電話しても、用意されている幾つかの質問事項に答えるよう促され、チェックシートを淡々と読み上げられるだけ。こっちがいくら家庭ではもう対応出来ませんと言っても帰って来る言葉は『もっと重症の人のために、病院のベッドは確保しておきたいので、息子さんの症状ではもう少しご家庭で対応してください。』の繰り返し。」泣きながら話す母親の声を聞きながら、電話は使えるのか・・・と不思議な感覚になっている自分に気づく。
「いつの時代も同じ。この国の政治家は、社会がこういう状況になるとを専門家が予測し警鐘を鳴らしてもそれに耳を傾ける事をしない。最初に自分たちが描いた作戦は何があっても軌道修正せず、楽観論と精神論だけで事態を切り抜けようとする。仮に途中で政策が間違えだったと気づいても、間違ったのは自分たちの責任ではなく、国民がルールを守らなかったから、或いは社会状況が想定外に変化したからと言い逃れ。責任の取り方を記者会見で問われても『今の状況を改善するのがリーダーとしての私の責任です』の一点張り。おまけに「今開催中のオリンピックとこの状況は関係ありません」って何よ!」
普段は優しい僕の彼女が、とても怖い顔でゲリラ豪雨の時の雷鳴の様に怒りをまき散らしている。医療が逼迫している状況下でも、この国ではオリンピックが行われているのかと、かなりやばい重傷者の僕なのに自然と笑いがこみ上げて来た。呆れたときや諦めた時に笑いが出る事があるという話は国語の授業で聞いたことがあったが、死が迫っている状況でもこの手の笑いがこみ上げて来ることを僕は初めて知ることが出来た。
僕はこのまま死ぬのだろうか。今年の夏は彼女とプールや夏祭りに行きたかった。毎年恒例の家族旅行にも。国は緊急事態だから今年の夏休み『は』自粛せよと言うが、今年の僕の夏休みは今年『だけ』なんだ。政府が今回のオリンピックを開催する理由の一つに、「オリンピックは4年に一度『だけ』なんです。それに向けて頑張ってきた選手のためにもオリンピック『は』開催致します。」と首相がカメラに向かい話していたのを、僕ははっきりと憶えている。
目に見える頑張りをしないと国は認めでくれないのだろうか?確かに僕らは選手と同じ種類の頑張りはしていない。つまらない事で悩んだり、すぐに諦めようともする。それでも後ろ指指されるような生き方はしていないぞ。素朴に地道に毎日を生きている。言葉には出さなかったけれど家族が喜ぶ事が大好きで自分なりに頑張ってきた。誰かのためにそっと手を貸す準備だって、いつでも出来ていた。目立つもの『だけ』が重要で、目立たない者に『は』想像力が及ばない政治家や政策。この国で生き残るためには、目立つ事をすることが必要だったのか…。
「政治家の皆さん、僕の人生も一度『だけ』ですよー!!」
遠のいていく意識の中で最後に思った言葉はこれであった。そして泣きながら洞窟を飛び出して行く彼女の痩せた後ろ姿がぼんやりとだが見えていた。人生の情けない終わり方に、僕の目からは目立たない一滴の涙が零れた。
つづく
2021.8.6
霞ヶ関高等学校
副校長 伊坪 誠